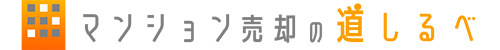promotion
「抵当権設定登記を行うのに必要な書類が知りたい」「できれば安く抵当権を登記したい」
抵当権設定登記とは、住宅ローンを借りる際に、融資した金融機関が抵当権を設定する手続きのことです。
この手続きは銀行が自動的に行ってくれるわけではなく、融資を受けた人が法的に手続を行わなければいけません。
そこで今回は、抵当権設定登記とは何か、依頼の流れや費用と自分で申請する場合の手続きも解説します。
これから住宅ローンを借り入れる人、または家を購入する予定がある人はぜひ参考にしてください。
もくじ
抵当権設定登記を実施する目的

まずは、抵当権とは何か簡単におさらいしましょう。
抵当権とは、住宅ローン等の融資を受けた際に、「返済できなかったときは家を売却して、貸したお金を回収しますね」という形で、住宅を取り上げる権利を設定するものです。
抵当権を所有するのは、もちろん融資した金融機関で、万が一支払いが滞ったときには、抵当権を設定した該当不動産が金融機関に回収されます。
このとき金融機関が「この不動産の抵当権は私のものですよ」と公にツバをつけることが抵当権設定登記です。
つまり抵当権設定登記とは、不動産に抵当権が設定されているという証拠として残すための措置となります。
抵当権設定登記を行う必要がある5つのパターン

抵当権が必要となるのは、融資を受ける場合と説明しましたが、具体的にどのようなときに必要となるのでしょうか。
抵当権を設定しなければいけない状況は以下になります。
|
このように、ほとんどの場合がお金を貸し借りする場合に抵当権が設定されます。
いずれにせよ「どうしてもお金を返してくれないと困る」という場合に、返済の証拠として抵当権が設定される傾向です。
抵当権設定登記を実施するタイミング

住宅ローンを借り入れ、融資が実行された後に抵当権設定登記を行います。
ただし存在していない建物に抵当権を設定することはできないため、多くの場合には建物が完成し、所有権が移転されたタイミングで、抵当権が設定される流れです。
家を建てる場合、先に土地を引渡して後日建物を建てる場合があります。
このような場合には、金融機関によって設定のタイミングが異なりますが、「家と土地をそれぞれに設定登記をする」「後日まとめて設定登記をする」という方法のいずれかを選択するのが一般的です。
先に土地の抵当権を設定した後で建物完成後にもう一度抵当権を設定するのか、建物が完成したタイミングでまとめて抵当権を設定するのかを金融機関と話し合い、納得のいく形で手続きを進めていきましょう。
抵当権設定登記を司法書士に依頼する方法

通常、抵当権設定登記は司法書士の専門業務のひとつです。
金融機関から紹介される場合もありますが、個人で司法書士に依頼するという方法もあります。
抵当権設定登記を依頼するには、金融機関で紹介してもらうか、個人で司法書士事務所へ問い合わせ抵当権設定登記の手続きを依頼する流れです。
司法書士に依頼するタイミングは、融資を受ける前の段階となります。
司法書士立会いのもと金銭消費貸借契約を締結し、融資関係の書類を司法書士に託すことになります。
抵当権設定登記を行う際の費用相場と内訳

司法書士に抵当権設定登記した場合の相場は、約3~5万円です。
この費用の内訳は以下のようになります。
|
抵当権設定登記に必要な書類の中には、個人で申請してもお金がかかる有料の書類があります。
費用のほとんどが書類申請時に必要な手数料と司法書士への依頼料です。
もし、申請に必要な権利証がなかったり、抵当権設定先が複数ある場合には、約2~4万円費用が割増しとなるので注意しましょう。
司法書士の依頼料を少しでも安くする方法

法律の専門家である司法書士へ抵当権設定登記を依頼すると、自分で登記をするときよりも費用がかかります。
もし司法書士への依頼料を少しでも削減したい場合は、不動産の権利証や家屋証明書などの必要書類は自分で用意するようにしましょう。
また司法書士への依頼料については、複数の司法書士事務所を比較し、少しでも安いところを選ぶという方法もあります。
ただし、法務局へ申請するための税金などは値引きできないため注意が必要です。
信頼できる司法書士を選ぶ時のポイント

できるだけ安く司法書士を雇いたいとはいっても、対応がいまいちだったり手続きが遅かったりしたのでは、スムーズに不動産取引を終えることができません。
そのため司法書士は安さだけを重視するのはなく、信頼できるかどうかもチェックしていきましょう。
司法書士を選ぶときはこれまでの実績と依頼する仕事を専門としてやってきたかを確認してみてください。
また、知人などの紹介で司法書士を選ぶのも信頼関係を構築するために重要なポイントです。
抵当権設定登記を自分で実施する方法

抵当権設定登記費用をできる限り安くするために、自分で登記を行うという方法もあります。
しかし登記はとても手続きが難しく、個人が簡単にできる手続きとは言えません。
そこで、少しでも手続きがスムーズにいくよう、自分で登記を行う場合の必要な書類と申請方法を紹介します。
抵当権設定登記に必要な書類
抵当権設定登記を行うために必要な書類を紹介します。
| 書類名 | 交付場所 | 費用 |
| 金銭消費貸借契約書 | 金融機関から交付 | 金融機関による |
| 登記事項証明書 | 法務局かWEBサイトにて申請 | 1通480~600円 |
| 印鑑証明書 | 市町村の窓口 | 1通300円 |
| 実印 | 所有者が所持しているもの | 自宅にあるもの |
申請に使用する書類は、それぞれ別の窓口で交付されることになります。
発行手数料が必要なものもあるため、事前に準備しておきましょう。
抵当権設定登記の申請方法
書類を整えたら、法務局にて抵当権設定登記を行います。
おおまかな手順は以下の通りです。
| 抵当権設定登記の申請の流れ |
| 1.金銭消費貸借契約を金融機関で締結する
2.抵当権設定契約 3.法務局にて登記申請 4.抵当権設定登記 5.抵当権設定登記された登記事項証明書を金融機関へ提出 |
以上が抵当権設定登記の流れとなります。
抵当権設定登記にかかる日数
上記の抵当権設定登記手続きが完了するまでの期間は、7~14日程度です。
法務局の混在状況にもよりますが、平均すると長くて半月以内には登記申請が完了します。
申請をしてすぐに登記が完了するわけではないため、売却スケジュールによって申請時期を定めていくことが大切です。
住宅ローンを借り換える場合の抵当権設定登記に関して

住宅ローンの融資を新たに受ける場合は、抵当権設定登記だけでいいのですが、住宅ローンを借り換える場合は、手続きがもう少し複雑です。
借り換えとは、ひとつの住宅ローンを終わらせて別の融資を受けるため、終了させる方の融資には抵当権抹消登記の手続を行わなければいけません。
抵当権抹消登記にも登記手続きの費用が必要なので、あらかじめ費用を準備しておきましょう。
抵当権設定登記に関するQ&A

ここまで抵当権設定登記について紹介してきましたが、上記の解説以外にも登記手続きに関する疑問が出てくると思います。
そこで、よくある抵当権設定登記に関するQ&Aをまとめたので、参考にしてください。
Q1.根抵当権設定登記とは?
根抵当権とは、複数の借金をまとめて担保している場合に設定する権利です。
カードローンのように借入に対して一定の限度額を設け、限度額を超えない範囲で借りたり返済したりを繰り返す場合に担保される権利のことです。
根抵当権は元本が確定された場合、抵当権と同じ扱いとなります。
借入の方法が異なるだけで抵当権設定登記とほぼ変わりありません。
Q2.抵当権設定登記の委任状って?
登記は原則として当事者が行う手続きですが、知識もない個人が行うには少々難しい内容です。
そのため、司法書士に登記を依頼する人がほとんどですが、その際に「司法書士に登記を依頼します」という本人からの委任状が必要となります。
委任状がない場合、司法書士は抵当権設定登記を行うことができません。
Q3.抵当権設定登記を実施しないとどうなる?
仮に抵当権設定登記をしない場合はどうなるのでしょうか。
実は抵当権設定登記をしなくても設定された抵当権は実行されます。
また登記をしていないからと言って、借金が帳消しになることにはなりません。登記をしなくても担保された不動産は有事の際に回収されます。
Q4.個人からお金を借りて購入した場合も抵当権の設定は必要?
「抵当権設定登記を行う必要がある5つのパターン」で少し触れましたが、個人間でお金を貸し借りした場合も抵当権設定登記は可能です。
抵当権の設定は強制ではないため、設定するかしないかは当事者の自由となります。
ただし個人間の借金の場合、話がこじれてしまいトラブルが発生してしまうかもしれません。
個人間で抵当権を設定する場合にも、法律の専門家に借用書の作成を依頼するなど、法的な手続をとることをおすすめします。
まとめ
抵当権設定登記は、住宅ローンのような大きな金額の融資を受ける際に、金融機関から設定される担保手続のことです。
抵当権設定登記は正確性が重要なため司法書士のような法律の専門家に依頼されます。
抵当権設定登記手続きは、司法書士に依頼した場合は3~5万円程度の費用がかかり、手続が完了するまでには約7~14日ほど必要です。
もし抵当権設定登記の費用を節約したい場合には、登記事項証明書など必要書類をできるだけ自分で用意したり、自分で登記を行ったりするという方法があります。
詳しい抵当権設定登記に必要な書類と手続については、これまで紹介してきた内容を参考にしながら行ってください。
簡単な手続とは言えない抵当権設定登記ですが、スムーズに取引を終えられるよう信頼できる司法書士を探していきましょう。