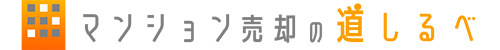promotion
夫婦が離婚するときには、所有していた財産(共有財産)を半分ずつに分けるのが原則です。
しかし、財産分与におけるマイホームの取扱いは難しいことが少なくありません。
「半分に分ける」ことのできない財産であるだけでなく、最も財産価値の高い財産である場合がほとんどだからです。
また、配分するのは財産だけでなく、住宅ローンなどの負債も分配の対象になるので、より複雑になります。
そこでこの記事では、家を財産分与するときの方法や注意点などについて、不動産のプロである筆者が解説していきます。
離婚の際には、「財産分与なんて後で良いからとにかくいますぐ離婚したい」と考える人も少なくないようです。
しかし、財産分与は、離婚後の生活を考える上でとても重要な問題です。
ちょっと面倒と考えている人でも、一歩立ち止まって冷静に検討しておきましょう。
もくじ
離婚後の家の財産分与の概要

夫婦が離婚する際の財産分与についての3つの基本的事項、
- 財産分与の対象になるもの、ならないもの
- 夫婦の財産分与の比率
- 財産分与を行う時期・タイミング
について確認しておきましょう。
①財産分与の対象になるもの、ならないもの
財産分与の対象になるものの主な例としては、
- 家
- 土地
- 家財
- 自動車
- 年金
- 保険
- 株などの有価証券
- 住宅ローン、自動車ローン
などが挙げられます。
額面でわかりやすく分割できるものはいいですが、家や自動車は半分に割って分割するわけにはいきません。
別の資産で相殺をしたり、売却して現金化した上で分配するのが一般的です。
また、「マイホームは夫名義のものだけど、財産分与の対象となるのだろうか?」と不安に感じている人もいるかもしれません。
しかし、離婚した際には「夫婦が婚姻中に協力して取得した財産のすべて」が財産分与の対象となります。
住宅ローンを支払っているのは夫だけという場合でも、住宅ローンを支払えるようにするために、妻が貢献していると考えることができるからです。
ちなみに婚姻生活中に夫婦が協力して得た財産は「共有財産」といいます。
他方で、婚姻生活とは無関係に得た財産を「特有財産」といい、こちらは財産分与の対象とはなりません。
たとえば、
- ・配偶者が自分の親から相続した家(不動産)
- ・配偶者が結婚前から所有していた家(不動産)
は、離婚した際の財産分与の対象とはなりません。
②夫婦の財産分与の比率
夫婦の財産分与の割合は、「共有財産を半分ずつ折半する」のが原則です。
妻が専業主婦で一切収入がないという場合でも、「1/2ずつ」となります。
なぜなら、「夫が安心して働きに行けるのは、他方が家事を負担し家庭を支えているから」といえるからです。
法律の世界でもいわゆる「内助の功」をきちんと認めてもらえるのです。
ただし、「1/2ずつ折半する」のは、あくまでも「基本的な考え方」に過ぎません。
たとえば、裁判手続きで財産分与を決めるときには、
- 共働きであるのにも関わらず、夫婦の一方のみが家事を全部負担していた
というような場合には、家事を負担していた配偶者の方が家計に対する貢献度が高いとして、多くの財産分与を認められることもあります。
また、協議離婚のときには、分与の割合は離婚する夫婦が協議して自由に定めることも可能です。
最近では、ビートたけしさんが、財産のほとんどを妻に譲って離婚をしたことが話題にもなりましたよね。
③財産分与を行う時期・タイミング
実際に離婚するケースでは、「財産分与に時間がかかるなら何もいらないからすぐに離婚したい」と考える人も少なくないようです。
特に、感情的になっているケースでは、相手への見栄やその場の勢いなどで強行的に離婚してしまうこともよくあるそう。
しかし、実際に離婚してみてから、「生活が苦しい…」「やはり財産分与すべきだった…」と思い直すこともあろうかと思います。
そのような場合でも、「離婚から2年以内」であれば、別れた配偶者に財産分与を請求することができます(民法768条2項ただし書き)。
しかし、離婚後に財産分与をすることは、次の点でリスクがあります。
- ・夫婦が別々に生活することになるので、協議の時間を確保するのが難しい
- ・別れた配偶者が、共有財産だったのものを費消してしまう可能性がある
- ・なにが共有財産であるか不明確になってしまう
したがって、財産分与は「離婚するとき」に同時に行うのが最も賢明といえます。
離婚後に家を夫婦で財産分与する際の3つの方法

離婚する夫婦が家を財産分与する方法には、
- 夫がそのまま家に住み続ける
- 妻が家を取得する
- 家を売却し代金を分与する
の3つの方法があります。
今回は、「夫が家の名義人である」と仮定した上で、解説していきましょう。
➀夫が今の家にそのまま住み続ける場合
夫名義の家に夫がそのまま住み続ける(離婚した妻が家を出ていく)という場合は、マイホームについては、特段の手続きは不要です。
しかし、財産分与では、共有財産を折半しなければならないので、それに相当する財産を分与しなければなりません。
たとえば、マイホームの価値が2,000万円で、他の共有財産(預貯金・現金など)が2,000万円という場合であれば、他の共有財産をすべて妻に与えなければならないということです。(※住宅ローンを完済しているケース)
仮に、マイホーム以外の財産がほとんどないというときに、マイホームを一方だけが引き受けるという財産分与をすれば、「贈与税の対象」となる可能性もあります。
贈与税の課税を免れるためには、夫が現金で妻に半分の1,000万円を支払うなどして、財産分与の比率を守らなければいけません。

➁妻が家を取得する
家の名義人である夫が離婚後は家をでて、名義人ではない元妻側に与えるという場合には、マイホームの所有者名義を変える必要があります。
財産分与に伴う名義変更は、「贈与」や「売却」とは違うので、贈与税や譲渡所得税はかかりません。
ただし、共有財産のうち最も金銭的価値の高い不動産を一方だけが取得することで、他の共有財産の分与が難しくなることは、夫がそのまま住み続ける場合と同様で、現金等で相殺する必要があります。
➂住宅ローンが残っているとさらに面倒なことに
住宅ローンが残っているときには、ローン債権者の同意がなければ、次の対応をすることができません。
- ・マイホームの名義人の変更
- ・連帯保証人の解除
たとえば、名義人である夫がそのままローンを負担し家に住み続けるという場合でも、妻が連帯保証人となっていることもあるでしょう。
この場合には、債権者の同意がなければ、妻は連帯保証人から外れることはできません。
「代わりの連帯保証人が見つけられない」というときには、妻は離婚をして全く無関係になった住宅ローンの連帯保証人であり続けるほかありません。
逆に、ローンを負担していない妻にマイホームの名義を変えるときには「妻がローンの残りを引き継ぐ」が最も公平といえます。
しかし、妻にローンの支払い能力がなければ、債権者の同意が得られないこともあるでしょう。
※家を出て行く側がローンを支払い続けるケースについては、下で別に解説しています。
「家を売却する」のがベストのケースが多い

離婚をする際に、共有財産であるマイホームにどちらかが住み続けることは、不可能ではありません。
しかし、さまざまな手間がかかる場合が多く、その後の対応をめぐって、しこりが残ることも珍しくありません。
その意味では、離婚するときには、マイホームを売却して現金化してしまうのが、財産分与の観点では、もっともシンプルで後腐れのない方法といえます。
また、マイホームを売却して財産分与することを選択したときには、「1円でも高く売却する」ことにこだわるべきでしょう。
独身生活になれば、これまでよりも生活費の負担が重くなることが多いので、今後の生活のためにもできるだけ多くの財産を手元に残すことがとても大切だからです。
離婚の際には、「早く離婚したい」と、種々の手続きを疎かにしてしまうことも多いのですが、「離婚をして他人になる」からこそ、いまの財産の処理には、万全を尽くしたいものです。
~今月の人気記事~
家の売却時に570万円以上損をしてしまうことも!?
不動産査定サイトを使わないと大損をしてしまう理由と35サイト徹底比較
家を売却する前に確認しておくべき3つのポイント

具体的に、家の財産分与について説明していく前に、事前に確認しておくべきポイントについてお話しておきます。
押さえておいて欲しい点は以下の3つ。
- 家の名義人
- 住宅ローンの名義人とローン残債
- 家の査定額
それぞれ解説していきます。
①家の名義人
まず確認しておくべきなのは、「家や土地の名義人は誰なのか」という点です。
もちろん覚えている人が大半だと思いますが、万が一忘れている人のために、名義人の2つの確認方法について紹介しておきます。
一つ目の方法は、法務局に行って600円の手数料を支払うことで、登記簿謄本を取得すること。
二つ目の方法は、オンライン上で請求する方法で、郵送の場合は手数料500円、直接受け取りに行く場合は400円の手数料で済ませられます。
具体的には、「登記ねっと 不動産登記手続き」にアクセスし、請求すればOKです。
②住宅ローンの名義人&保証人とローン残債
住宅ローンの名義人&保証人に関しては、借り入れを行っている金融機関に問い合わせることで確認できます。
夫が単独で借り入れをしているのか、妻が連帯保証人になっているのか、共同名義での保有なのかなど、パターンが変わってきます。
合わせて、住宅ローンがいくら残っているのかも確認しておきましょう。
家の価値は、査定額ーローンの残債で決まるので、忘れないよう気をつけてください。
③家の査定額
財産分与を行う際には、家の価値がいくらなのかを把握しておく必要があります。
家の査定を行う方法は大きく2つあって、
- 不動産会社に無料で査定を依頼する
- 不動産鑑定士に有料で査定を依頼する
のどちらかを選ぶことになります。
①の不動産会社への査定依頼の場合、費用はかかりませんし、複数社に査定を依頼した上での金額であれば信憑性も高いです。
ただし、不動産会社が査定を無料で行うのは、その後に売却の依頼を請け負いたいからです。
当然ビジネスとして査定を行うので、依頼をした後は売却に誘導されることは覚えておきましょう。
また、専門の国家資格を持った不動産鑑定士に依頼する場合、評価額に応じて数十万円程度の鑑定料がかかる代わりに、信憑性の高い査定額が分かります。
不動産鑑定士は売却を促してくるようなこともないので、2つの査定のどちらを選択するかは総合的に判断するといいでしょう。
売却後に残ったお金の分配方法は?

不動産を売却した場合の売却額は、夫婦で「1対1に折半する」のが最も基本的な分配方法です。
もっとも、協議離婚の場合であれば、分与の割合を自分たちで自由に決めることができます。
実際にも、有名人の離婚では、一方の配偶者のみが多額の財産を手にするようなケースもないわけではないようです。
しかし、通常の限度を超えた形で、片方のみに財産が分与される場合には「贈与」したという扱いになるので、「贈与税」が発生してしまいます。
住宅ローンの残債が売却価格よりも高いオーバーローンの場合の対処法3つ

離婚する際にマイホームを売却したくても「住宅ローンの残り」がネックとなる場合があります。
住宅ローンの残っている不動産を売却するためには、抵当権者(住宅ローンの債権者もしくは保証会社)の同意を得なければならないからです
売却額がローン残額よりも大きいのであれば、売却額でローン残額を清算して、残ったお金を夫婦で折半すればよいのですが、ローン残額が売却額よりも大きい「オーバーローン」のときには、そうはいきません。
売却(抵当権抹消)について抵当権者の同意を得るためには、住宅ローンを完済することが条件となるのです。
そのため、住宅ローンの残債が売却価格を上回る場合は、以下3つの方法で対処する必要があります。
➀自己資金で差額を返済
ローン残額と売却額との差がさほど大きくないときには、売却額では支払いきれなかった住宅ローンを預貯金などの自己資金で完済することがベストの対応でしょう。
住宅ローン清算後の財産は、夫婦で折半するのが最もシンプルで後腐れのない方法ではないでしょうか。
➁無担保ローン等を借り入れて差額を返済
住宅ローン残額を支払えるだけの自己資金がないときには、残額相当額を無担保のローンで借り入れる方法もあります。
とはいえ、ローン残額が大きいときには、ローンの審査に通らないこともあるでしょう。
また、無担保のローンは金利の負担が重いので、その後の返済に行き詰まってしまう可能性も考えられます。
したがって、無担保のローンでローン残額を清算する方法は、マイホーム売却後のローン残額が少ない場合を除いては、正直あまりおすすめできません。
➂「任意売却」を行う
ローン残額を自己資金では清算できないときの解決方法として、「任意売却」するというのも一つの手です。
任意売却とは、「ローンを完済できないとき」に抵当権者の同意を得て、不動産を処分することを言います。
「そんな都合の良い方法があるの?」と思う人もいるかもしれませんね。
たしかに、通常の状態では、抵当権者は「オーバーローン物件の売却」には同意してくれません。
そこで、任意売却をするためには、「わざと住宅ローンを滞納して、強制競売される状況を作り出す」必要があります。
そのため、住宅ローンの滞納による強制解約(代位弁済実行)が原因で信用情報が汚れてしまうというデメリットが生じてしまいます。
関連記事→住宅ローン残債ありのマンションを売却する3つの方法|一括返済・買い替えローン・任意売却
家を売却した場合にかかる費用・税金まとめ

家を売却するときには、次のような費用や税金も発生します。
- ・不動産を測量するための費用
- ・売却するための立ち会いに応じてもらう心付け
- ・登記手続きの費用(登録免許税)
- ・登記手続きを司法書士に依頼した場合の報酬
- ・売買を仲介した不動産会社の仲介手数料
- ・売却によって多額の利益がでた場合の譲渡所得税
これらの費用は決して安いものではありません。
たとえば、宅地の測量費用は、30万円前後かかることが一般的ですし、不動産の仲介手数料も売却額の3%ほど支払うケースが多いです。
そのため、売却にかかる費用だけでも100万円を超える負担となることは珍しくないのです。
離婚の際には、「とにかく早く離婚をする」ということに関心がいってしまうことが多く、費用や税金のことには無頓着になりがちです。
しかし、離婚するからこそ、最もコストの少ない方法で売却する、最も高く売ってくれる業者を選ぶことが大切ともいえるでしょう。
家の名義を変更する方法・パターン

「売却には手間も費用もかかる」、「子どもを転校させたくない」といった事情から、家を売却せずに、そのままどちらかが住み続けるというケースも少なくありません。
特に「子どもが理由」で家を売却しないケースでは、子の面倒をみる妻が家も引き継ぐことが多いと思われます。
この場合、マイホームの名義が家を出て行く夫にあるときには、マイホームの名義を変更する必要があります。
住宅ローンを完済している場合の名義変更
マイホームの名義を変えるためには、法務局で「財産分与による所有権移転登記」の手続きをしなければなりません。
登記簿上の所有者の名義が変わっていなければ、「マイホームの所有者である」ことを第三者に主張することができないからです。
財産分与による所有権移転登記に際しては、次の点に注意する必要があります。
- 離婚後でなければ、登記手続きができない
- 夫婦の共同申請でなければならない
- 登記の日付は、財産分与の協議がまとまった日となる(離婚前に協議が成立していたときは離婚が成立した日となる)
- 登記手続きに登録免許税がかかる(評価額の2%)
- 登記手続きを司法書士などに依頼すれば報酬が発生する
また、登記の手続きには、下記の書類が必要となります。
- ・不動産の登記済証、または、登記識別情報通知(いわゆる権利証)
- ・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- ・印鑑(実印)
- ・固定資産評価証明書(登記をする年度のもの)
- ・離婚の記載のある戸籍謄本(もしくは調停(和解意)調書や審判書)
注意点をしっかりと把握して、必要書類の提出も忘れないようにしましょう。
住宅ローンがまだ残っている場合の名義変更
住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの債権者(お金を貸してくれている金融機関)の承諾が必要となります。
ローン債権者の承諾を得るためには、以下の対処が必要です。
- ローン残額を完済する
- 家に住み続ける側が所有者となりローンの残りを返済し続ける
- 家を出て行く側が名義人を変えてもなおローンを支払い続けることを確約する
理屈上は、ローン債権者(抵当権者)の同意無しに名義を変えることは可能ですが、住宅ローンの契約違反となる場合がほとんどです。(残額の一括返済を求められてしまいます)
妻が家に住み続け夫がローンを返済していく場合の3つのリスク

実際の財産分与では、「支払い能力のない妻がマイホームに住み続け、家を出た夫がローンを返済していく」ことが選択される場合が少なくないようです。
つまり、「慰謝料や養育費の代わり」として、夫がローンを負担していくパターンです。
しかし、家に住み続ける人と、ローンを支払い続ける人が異なる状況になることには、次のようなリスクがあることに注意しなければなりません。
- 別れた配偶者がローンの支払いを怠るとマイホームを差し押さえられてしまう
- 離婚後は別れた配偶者と連絡がとれなくなる可能性が高くなる
- 住宅ローンを完済するまではマイホームの名義を変えられない(自分の家にならない)
最も心配すべきは、別れた夫(配偶者)がローンの支払いを途中でやめてしまうこと。
自分が住んでいる家賃とは別に、住んでいない家の家賃を払い続けることは、決して楽ではありませんし、投げ出してしまう人も多いです。
また、離婚後の新しい生活に変化があれば、物理的に「ローンを支払えなくなる」こともあるでしょう。
「マイホームの名義を変えた」という場合でも、抵当権登記後の名義変更は抵当権者に対抗できないため、抵当権が残っている限りは、差し押さえの可能性は消えないのです。
特に離婚後は、関係が希薄なる夫婦も多く、こちらの知らないところで「失業していた」「病気になっていた」ということも十分ありえます。
また、離婚後にお互いの連絡が希薄になることは、ローンをきちんと支払っていた状態でも問題となる場合があります。
「別れた配偶者にローンを支払ってもらう」というケースでは、ローンの完済後に改めて名義変更(所有権移転登記)することになるからです。
名義変更は新旧両方の所有者の共同申請でなければならないので、別れた配偶者と連絡が取れない(手続きに協力してもらえない)ということになれば問題です。
せっかく買ったマイホームを手放したくないと考えるのは、自然な思いかもしれません。
しかし、別れた配偶者にローンを完済してもらうということは、長期間の間大きなリスクを抱えることにもなるということは、覚悟しておかねばなりません。
まとめ
離婚をするケースでは、「早くすっきりしたい」と考えるあまりに、十分に考えないで財産分与をしてしまうことも珍しくありません。
しかし、離婚後の生活は、婚姻生活のときよりもさまざまな費用負担は重くなってしまうことが一般的です。
お互いに、離婚後の新生活を気持ちよくはじめるためにも、離婚の際の財産分与は、それに必要なコスト、分与した場合のリスクもきちんと見据えた上で、お互いに納得・安心できる方法で行うことが大切でしょう。
マイホームは資産価値も高く、今後の生活にも大きな影響を与える問題なので、特に慎重に検討すべきといえます。