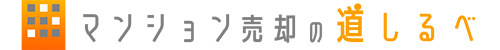promotion
「自然の中で暮らしながら生活したい」「将来的には地方でゆっくりと暮らしたい」
騒がしい都会暮らしに疲れ、田舎でのんびり暮らしたいとお考えではありませんか?
自然が多く心身ともに健康的な生活を送れそうな地方への移住ですが、就職先や交通の便など、ライフスタイルが一変することも視野に入れなければいけません。
田舎の良い部分と悪い部分をしっかりとリサーチしたうえで、地方に移住するかどうか検討していくことが大切です。
そこで今回は、地方移住のすすめ、セカンドライフを豊かに過ごす田舎暮らしの魅力と移住方法について紹介します。
これから地方へ移住したいとお考えの人は、ぜひ参考にしてください。
もくじ
地方移住のメリット3選

まずは、地方に移住することで得られるメリットからみていきましょう。田舎で暮らすことのメリットは以下の3つです。
- 子育てがしやすい
- 家賃が低い
- 自然が多い
ここからは、それぞれのメリットについて紹介します。
①子育てがしやすい
都会の喧騒からとは違い、自然豊かな地方では子育てをしやすいという特徴があります。
具体的なメリットとしては、自然環境の中で子育てができること、そして移住支援制度として助成金が受け取れるという点です。
地方は人気のない公園が多く、周囲の目を気にせずに子供をのびのびと遊ばせることが可能です。
また、自然が豊か地域に住むと、子どもに四季を感じさせることも可能です。
そして、過疎化を防止するために移住者には自治体から引っ越しの支援金として数十万円の助成金を受け取れるケースもあります。
このような助成金は、移住支援制度と呼ばれており、自治体ごとに支援内容が異なるため、移住を検討する前にしっかりとリサーチしておきましょう。
また、国立青少年教育振興機構が発表している「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」によると、 子どもの頃の体験が豊富な大人ほど、やる気や生きがいを持っている人が多いという調査結果が公表されました。
子どもの頃に動物や植物と関わったり自然環境の中で育つと、子供の意欲が向上するというデータがあります。
自然が豊かな地方で子育てをすると、暮らしやすさだけでなく、子供の発育に関しても恩恵を受けることが可能です。
②家賃が低い
都会と比較すると地方の賃貸住宅の家賃は低い傾向にあります。
2019年2月に公表された全国賃貸管理ビジネス協会の「全国家賃動向」によると、以下のようなデータがみられました。
| 都道府県 | 1部屋あたりの平均家賃 | 前年度比 |
| 全国平均 | ¥49,542 | 3.3% |
| 東京都 | ¥67,512 | 1.0% |
| 大阪府 | ¥53,758 | 2.7% |
| 鳥取県 | ¥38,827 | -5.5% |
| 沖縄県 | ¥44,728 | -5.3% |
上記のデータによると、一番家賃が高い県は東京都の¥67,512で、最安値を記録したのは鳥取県の¥38,827でした。
全国平均値をみても、地方は首都圏に比べて¥28,685ほど賃料が安くなっていることがわかります。
また、前年度と比較しても地方の家賃の値下げ幅は大きく、減少傾向です。
以上のことから、賃貸住宅に住む場合は都心よりも地方の方が賃料負担は低いと言えます。
③自然が多い
自然が多いことは住みやすさにも繋がります。
河川環境研究室が公表している自然環境とのふれ合いが人間に及ぼす影響に関する基礎的研究によると、人が自然環境にいることでストレス負荷を示す唾液中コルチゾール・アミラーゼが低下したという研究結果となりました。
つまり、人が自然が多い環境で暮らすことは、ストレス緩和効果があり、リラックスした時間を過ごせるということになります。
国内で自然環境が多いのは、北海道、次いで岩手県、その次が福島県と東北地方は日本の中でも自然が多い地域です。
反対に自然が少ない地域は、香川県、次いで大阪府、その次は東京都となります。
地方である香川県は県内の面積が他県に比べ狭いため、上記のような結果となりました。
以上が地方に住むメリットになります。
これらのメリットは当たり前に感じる部分でもありますが、専門機関によるデータと照らし合わせると、より重要性が理解できるのではないでしょうか。
地方移住のデメリット5選

続いて、地方在住のデメリットについてもみていきましょう。
地方で暮らすことで、デメリットに感じてしまう点は、以下のようになります。
- 仕事が見つけづらい
- 車がないと不便
- 村八分、いじめに遭うケースも
- 飲食店や公共機関が不足している
- 意外と生活費が高い
こちらも、それぞれのデメリット部分について詳しく紹介していきます。
①仕事が見つけづらい
地方は都心部に比べると、「仕事が見つけづらい」「就職口がない」と感じている人が多いようです。
地方へ移住を考えているけれど実行に移せないと悩む人の多くは、このような仕事面での問題を重要視しています。
では、なぜ地方の仕事が少ないのでしょうか。労働製作研究所が公表している「地域雇用の現状と課題」を見ると、移住者の地域雇用が活性化しない理由は2つあるようです。
- ・認知度の不足・・・地元企業を知らないため就職口の選択肢になりにくい
- ・受け皿が狭い・・・就職先が役場・福祉・建設業などに限られてしまう
このような点から、「田舎は仕事がない」と感じてしまう人が多いようです。
地方の移住を決めるときは、地元にどんな企業があるのか、自分がやりたいことをやれる仕事はあるのかをリサーチしておいた方がいいかもしれません。
②車がないと不便
多くの場合、地方は車社会です。
車を所有していないと生活すること自体が難しくなります。
都心と比較すると、電車やバスなどの交通機関が少ないため、車がないと外出することすらままならない環境です。
また、建物が密集していないため、車がないと移動する距離と時間が長くなるどころか、車がないと目的地までたどり着けない場合もあります。
このような背景から、車は1人1台という地域もあるため、移住先によっては成人した家族分の車を用意しなければいけないことも考慮しておきましょう。
③村八分、いじめに遭うケースも
村八分とは、仲間外れという意味です。
地方の村八分は、主に地域のやり方や風習を守らずに好き勝手な生活を送ったり、出身地で差別が起こったりするケースがあります。
村八分に合うと、地域の人から一方的に無視される、地域の催し物に参加させてもらえない、子供の虐めなどの被害にあう恐れがあります。
実際に村八分が発生した過去の事件を紹介します。
- ・新潟県岩船郡関川村沼集落
- お盆のイワナつかみ取り大会の参加に不服を述べた住民に対して、集落の人間がゴミ集積所の使用禁止や山菜採りの禁止を命じた
- ・静岡県上野村村八分事件
- 替玉投票を告発した女子中学生に対し、村の有力者が村民に女子中学生への挨拶を禁じ、奨学金の使用を停止しようとした
すべての地域に村八分があるわけではありませんが、中には移住者を受け入れない、もしくは移住者に対して偏見を持っている集落があるかもしれません。
移住する場合は、希望予定地の移住者の数や風習をしっかりと確認しておきましょう。
④飲食店や公共機関が不足している
人口の少ない地方では、ファミリーレストランや居酒屋などの飲食店が多くありません。
地域によっては、コンビニに行くまで車で15分以上というところもあります。
そのため、都会暮らしであまり自炊をしない人には、生活しにくさを感じてしまうかもしれません。
また、飲食店以外にもカラオケやバー、ショッピングセンターなど娯楽施設がない地域もあります。
さらに、地方は車社会と紹介してきましたが、公共機関の不足も気になる問題です。
線路が通っていても電車は1時間に1本、乗り換えできる電車は3時間に1本というように、都心部では考えられないほど、公共機関の本数が少ない場合もあります。
自然が多いという部分だけにとらわれずに、周辺施設の有無もチェックしておくことをおすすめします。
⑤意外と生活費が高い
地方は家賃が安いと先述しましたが、実際に生活してみると都会よりも生活費が高いと感じてしまう人もいます。
地方の暮らしが意外と生活費が高くなってしまうのは「給与所得が少ない」「光熱費がかかる」という2つの理由が原因です。
厚生労働省が公表している「平成30年度地域別最低賃金改定状況」によると、1時間あたりの全国の平均最低賃金は874円というデータがあります。
東京都の最低賃金が985円なのに対し、青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・沖縄県の最低賃金は223円も低い762円です。
このことから、地方は家賃は安いけれど収入も低いということがわかりました。
また、地方では四季に気温差が激しい地域もあるため、エアコン代・灯油代・電気代が多くかかる恐れもあります。
さらに、車移動のためのガソリン代、積雪地では除雪代などが必要になる場合もありますので、移住先の気温や最低賃金もチェックしておいた方が無難です。
地方移住に失敗した人の事例5選

ここまで、地方移住のメリットとデメリットを紹介してきましたが、ここからは地方移住に失敗した人の事例もみていきましょう。
どんな点で失敗したのか、改善点はあったのかを確認し、今後の移住のために役立ててください。
失敗例1.いきなり移住先に移った
「地方移住のデメリット5選」でも紹介してきましたが、リサーチもせずにいきなり移住してしまうと後悔するパターンが多くなります。
地方に限らず、地域の風習や交通機関、周辺施設の有無を確認しないと、生活に不便を感じてしまうでしょう。
特に田舎は、「いつでも外食ができる」「遅くまで終電がある」というような都会の利便性はありません。
飲食店や公共機関は少なく、車がないと生活できない地域もあります。
このようなデメリット部分にどこまで対応できるかどうか、事前にリサーチしておくことがとても大切です。
ライフスタイルの変化は、時に大きなストレスを生んでしまうこともあります。
生活環境の変化に対応できるよう、移住先での暮らしのシミュレーションをしておきましょう。
失敗例2.地域の人とのコミュニケーションがうまくできない
地方では地域の人とのコミュニケーションが大切です。
「隣に誰が住んでいるかわからない」「顔を合わせても挨拶程度」という隣人との繋がりが希薄になっている都心部と比較すると、田舎では助け合いを基本としているため、人間関係を構築していかなければいけません。
毎日の挨拶はもちろん、ご近所さんとの飲み会や地域の行事に誘われる回数が増えるため、地域イベントに参加する機会が多くなります。
そのため、「人と話すのが苦手」「誰とも関わりたくない」という考えの人は、移住先でご近所さんと上手に付き合えないため、住みにくさを感じてしまうかもしれません。
全ての行事に参加する必要はありませんが、最低限付き合わなければいけない行事を事前にチェックしておいた方が無難です。
失敗例3.無計画に開業
のんびりとした雰囲気の中、カフェや居酒屋などを営みたいと思う人は少なくありません。
しかし、無計画な開業は失敗の大きな原因のひとつです。
移住先での開業が失敗する要因は、地域の習慣を理解していない、交通量を把握していないなどがあげられます。
開業を成功させるためには、需要と供給のバランスを把握し、適切な場所に必要な事業を立ち上げることが大切です。
一見、田舎のような何もない地域では、流行りのお店や目新しい商売を始めれば、すぐに顧客がつくように勘違いしてしまいますが、実際はそんなにうまくはいきません。
特産品を活用できる商品や、必要とされるサービスなど、地域の人が受入れやすい事業を計画的に立ち上げていく必要があります。
失敗例4.夫婦間での温度差
移住計画が夫婦どちらかの強い意志によるものだった場合、移住に賛成ではない方からの不満が大きくなってしまう場合があります。
「本当は移住したくないのに無理に引っ越しさせられた」「良い暮らしができると言われたのに想像と違った」など、不満が大きくなってしまうと夫婦喧嘩が絶えなくなり、最悪の場合には離婚問題にまで発展してしまうかもしれません。
移住生活は、実際に生活をしてみないとわからないものです。
相手が移住に乗り気じゃない場合には「絶対に楽しい」「きっと気に入るはず」という根拠のない説得はやめて、移住先に旅行してみたり移住したい具体的な理由を述べて納得させたりするなど、相手に引越しを理解してもらうように努めましょう。
失敗例5.仕事が見つけられない
地方で仕事を見つけることができない理由は2つあります。
まずひとつは、求人情報がほとんどない、そして募集している職業に偏りがあるという点です。
都心では、求人誌やWEBサイトにアルバイト情報が豊富に掲載されていますが、地方では情報自体が掲載されていない場合もあります。
また、募集している職業が臨時公務職や介護・看護職などが多く、デザイナーやエンジニアなど都会で活躍できるような職種が少ない状態です。
移住先で募集している職種が偏っていると、自分に合った仕事が見つけられず仕事探しが難航してしまいます。
移住先で暮らしていくためには、家探しよりも仕事探しを優先的に考えた方がいいかもしれません。
このように、地方移住に失敗した人の多くが頭を抱えてしまった事例です。
「住んで良かった」と思えるようにするために、上記の例を参考にしてみてください。
地方移住で成功している人のブログ3選

ここまで移住に失敗した人の事例を紹介してきましたが、ここからは移住をした結果、新しい生活を成功させている人を紹介します。
実際に移住を成功させている人のブログを参考に、移住のヒントを見つけていきましょう。
カフカ氏「旅するカフカ」
旅するカフカは、世界各国を旅しながら渡り歩く男性のブログです。
移住を前提としたライフスタイルを重視しており、特定の住所を持たずに自由に暮らす様をブログで紹介しています。
畠山千春氏「ちはるの森」
ちはるの森は、福岡県糸島に移住し猟師をしながら暮らしている女性のブログです。
ブログでは薪を割り、暖を取る生活や、野生動物をさばいて美味しく調理したことなどが綴られています。
イケダハヤト氏「まだ東京で消耗してるの?」
まだ東京で消耗してるの?は、高知県高知市に移住位した男性のブログです。
田舎暮らしのメリットだけでなく、田舎で生活しながらも年収を上げる方法やガジェット系の記事も配信しています。
地方移住を行うまでの7つのSTEP

地方へ移住するためには、いくつかの手順を踏まなければいけません。
移住の理由や希望する暮らしは十人十色ですが、移住を成功させるためには基本的な流れを把握しておく必要があります。
移住するまでの基本的な手順は以下の7STEPです。
- 移住の目的を明確にする
- 家族やパートナーからの理解を得る
- 条件にあった移住先をリストアップする
- 可能な限り短期間で事前に住んでみる
- 住まいを探す
- 仕事を探す
- 引っ越し
移住するための流れを理解し計画的に引っ越しを進めることで、移住先で土台を造ることができ、今後の生活がスムーズになるでしょう。
ここからは、移住するまでの基本的な流れを順番に解説していきます。
①移住の目的を明確にする
まずは、なぜ移住したいのか、移住の目的を明確にしましょう。
「田舎暮らしに憧れている」「都会から脱出したい」「人間関係をリセットしたい」という漠然とした理由だと、移住後に「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまう可能性が高くなります。
移住の目的は「漁業をやりたい」「子どもを自然の中で育てたい」「移住先で支援を受けたい」など、働き方や家族の生活スタイルを明確にし、目的を叶えられる場所を探しましょう。
目的を明確にすることで、移住の決断がしやすくなると同時に、引越し先でやりがいを見つけることが可能です。
「どこに住みたいか」ではなく「何をやりたいか」に焦点を当てて考えてみると、移住計画が立てやすくなります。
②家族やパートナーからの理解を得る
家族やパートナーがいる場合は、全員の理解や協力が得られなければ移住は難しいと言えます。
移住したい明確な目的をきちんと話し合い、必ず家族全員の同意を得るように心がけましょう。
話し合いもしないままに強引に押し切ってしまうと、家庭崩壊のリスクが高まります。
そうならないためには、移住の理由と共に引っ越すメリットや不安点をひとつずつ解消させるなど、焦らずに話し合いを重ねましょう。
街並みの美しさ、生活費の増減、進学先についてなど、家族が魅力的に感じる部分を探り、アプローチをかけていきましょう。
話し合いがまとまらないときは、現在の住まいと移住先を行ったり来たりする二地域住居にすることや、一定期間別居するという手段もあります。
③条件にあった移住先をリストアップする
移住の目的を叶えられる移住先をいくつかピックアップしてみましょう。
根拠もなく「何となくここがいい」「生活費がかからなさそうだから」と移住先を決めるのは危険です。
自治体の施策や周辺施設、環境など、移住先でこだわりたいポイントをいくつかピックアップして、移住先を決める条件を書き出し、候補地をリストアップしていきましょう。
リストアップするときには、条件を満たせるかどうか、地域のメリットやデメリットを挙げていくと候補地を断定しやすくなります。
④可能な限り短期間で事前に住んでみる
いきなり移住を決めるよりも、できれば短期間でも構わないので、候補地に住んでみましょう。
自治体では、お試し住宅を利用できたり、暮らし体験ツアーに参加できたりします。
お試し住宅とは、1週間~2ヶ月の間、自治体が提供する住まいで暮らすことが可能です。
料金は1日約1,000円で光熱費や生活用品は実費で用意するシステムとなります。
また、暮らし体験ツアーは、移住先の風習や特産品を知るために街歩きや散策が体験できます。
ツアーは、1~2日間と週末にでも気軽に参加できるため、旅行気分で移住先の様子をリサーチしてみてはいかがでしょうか。
移住先の生活を想像してみるよりも実際に生活してみることで、移住計画が立てやすくなるため、引越し前に体験してみてください。
⑤住まいを探す
住まいは、自治体の移住支援制度か地元不動産から探していきましょう。
近年、地方の空き家問題を解消するために、空家を移住者に安く提供している自治体もあります。
このような取り組みは、空家バンク制度と呼ばれ、移住者の支援制度と深く関わっています。
空き家バンクから住まいを探すと、自治体により住まいの提供以外にも様々な支援がうけられます。
支援内容は、移住者に空き家を活用してもらえるよう情報提供や地元民との交流などです。
空き家物件は地方公共団体のWEBサイトに掲載されているので、ぜひ一度チェックしてみてください。
⑥仕事を探す
移住先では就活情報を見つけるだけでも大変です。
田舎で仕事を探すときは、ハローワークへ登録や、自治体によるUIターン転職相談窓口を活用してみましょう。
また、農林水産省では農業次世代人材投資資金という就農者への支援制度を提供しているのでチェックしてみてください。
この支援制度では農業をはじめるための補助金(最長2年間、 年間150万円)を受けられたり、農家同士の交流会に参加できたりもします。
補助金を受けるためには、45歳未満であることや自営するなど一定の条件があるので、注意しましょう。
⑦引っ越し
移住後の生活についてメドが経ったら、いよいよ引っ越しです。
引っ越し前には生活資金を多めに確保し、万が一の時に備えるようにしましょう。
引越しが住んだら、地域の区長や自治体の人へ挨拶を行ってください。
ご近所付き合いを大切にする地方では挨拶を重視しているところもあります。
挨拶をすることで、今後のトラブルを回避することや、地域の人の輪に溶け込みやすくなるでしょう。
挨拶するときには、手ぶらではなく粗品を配るのが一般的です。
誰に挨拶すればいいのか不明な場合には、引越しに協力してくれた自治体の人に相談するのもひとつの手段となります。
地方移住先でも収入を得やすい仕事ランキング5選

移住先での仕事探しは、移住を成功させるための大切なポイントのひとつだと解説してきました。
そこで、地方移住先でも収入を得やすい仕事をランキング化しました。
1.地域おこし協力隊
地域おこし協力隊とは、移住者向けに用意された短期雇用の支援員です。
主な仕事内容は、地産品の開発や販売、PRなどになり、地域活性化のために協力活動を行うことを目的としています。
期間内に地元民との交流を図り、起業や事業継承するための支援もうけることが可能です。
地域おこし協力隊とは、自治体から委託を受けた社団法人JOINが運営している地域活性化のための交流を推進している団体です。
総務省・各企業・自治体と連携し、若い世代の田舎暮らしを応援し地方移住のためのサービスを提供しています。
2.医療系
地域でも都心部と同じように需要がある仕事は、介護や看護などの医療系の職業です。
助手や受付など資格がなくても働けるため、安定した収入を得たい人におすすめの仕事になります。
収入を増やしたいときには、夜間学校に通う・通信教育を受けるなど働きながら資格を取得するという方法もあります。
医療系の資格は多岐にわたり、医療事務ひとつをとっても「診療報酬請求事務能力認定試験」「医療事務管理士」など、10種類以上の資格があるので、ぜひ就職を検討したい職業です。
3.農業
作物を育てたり、加工したり、販売したりするなど、農業には様々な仕事があります。
また、農家として作物を育てる傍ら、自然食材を利用した飲食店を経営するという方法もあります。
地方の過疎化防止策として、自治体による支援が受けられます。
専門家によるアドバイスや手当などがもらえる場合があるので、まずは移住を希望する自治体に問い合わせてみましょう。
4.事業継承
自治体によっては、後継者を求める事業主と事業を継承したい若者とのマッチング支援を行っています。
これにより起業をしなくても事業者として地域の産業に参加することが可能です。
地方では過疎化や人手不足により、業績は悪くなくても後継者がなく廃業を余儀なくされる起業が増加しています。
移住者による事業継承は、事業を行いたい移住者に事業を引き継いでもらい、経営を継続させる画期的な方法です。
移住者にとってはゼロから事業を開始するよりもリスクが低い起業方法とも言えます。
5.起業
近年インターネット起業が普及し、都会でも田舎でも起業ができる時代になりました。
人口が少ない地域でも、SNSで商品情報を拡散し、インターネットで注文を受け、商品を配送すれば収益を保つことが可能です。
地産品の布や毛糸を利用した洋服を販売したり、パンやジャムなどの加工品を製造販売したりと、様々な事業が行われています。
地域の人々だけでなく、国内に目を向けて色々なアイディアを発信してみましょう。
また、すでに廃業した商店街や地産品を使った商品開発や販売を目的とする起業の場合でも、最大で200万円の助成金が受けられる制度もあります。
ぜひ活用してみてください。
地方移住先でおすすめの地域ランキング5選

これまで紹介してきた交流推進機構JOINや移住支援番組のようなWEBサイトや情報番組で、おすすめの移住先が紹介されています。
それらの情報を参考に、評価が高い移住先を5つピックアップしました。
茨城県つくば市
茨城県の南に位置する地域で、日本国内最大の学術都市と言われています。
都内へ最短45分で移動できるため、首都圏への通勤も可能です。
移住者を支援する定住促進として農業体験ツアーや都内で交流会を開催しています。
空き家バンク制度に力を入れており、建設住宅政策課で空き家の有効活用方法が相談できます。
長野県駒ヶ根市
長野県の南部に位置する地域で、南アルプスと中央アルプスが望める自然豊かな土地になります。
商業施設が多く、田舎すぎないため暮らしやすいと感じる人は多いようです。
長野県は移住先ランキングで、長年上位に位置づけされている人気の地域で、特に駒ヶ根市では地域をあげて金融支援や就労支援など様々な移住支援を行っています。
山梨県甲府市
山梨県の中央に位置する地域で、最も人口が少ない県庁所在地です。
甲府市は山梨県の中でも都会化しているため、商業施設や医療施設が揃っています。
移住者を支援するための移住コンシェルジュの設置や、空き家改修制度、起業のための空き店舗紹介など、様々な取り組みを行っています。
高知県高知市
市国の南部に位置する地域で、高知県の県庁所在地です。
お酒やカツオのたたきが名物で、飲食店が多い地域でもあります。
高知市では、移住者のための就職情報の提供や起業・農業支援を行っています。
また、1つの空き店舗を2~3つの店でシェアするお試し開業支援などがあります。
カナダ
移住先として検討される人気の地域に、カナダがあります。
北アメリカに位置する地域で、移住申請している日本人は少なくありません。
カナダは移住国家でもあるため、日本人だからと言って偏見もなく自由に生活することが可能です。
気候も温暖で物価も安く、治安も良いため国外の移住先として候補に挙げられやすい国となります。
以上が、移住先としてお勧めの地域です。ぜひ参考にしてください。
東京23区内から地方移住したい人の支援を目的とした補助金の紹介

政府では、東京一極集中を防止するため、東京23区内から地方移住したい人の支援を目的とした補助金制度を用意しています。
内閣府では地方創生として、起業支援金・移住支援金を配布することを発表しました。
地方創生起業支援事業・地方創生移住支援事業
東京一極集中の是正及び地方の担い手不足対策のため、地方における起業、UIJターンによる起業・就業者を創出する地方公共団体の取組を地方創生推進交付金で支援します。
ここからは、支援金の概要と条件を紹介します。
適用となる詳細については各自治体へ問い合わせてください。
東京23区から特定の地域・事業で起業する人に最大200万円の支援金
起業支援金は、地域で起業したいと考えている人を対象にした人へ最大で200万円の支度金を支援する制度です。
支援の対象となる事業は子育て支援や地産品を使った飲食店など、まちづくりに関連したものであることが望ましいとされています。
この支援を受けるためには、以下のような3つの条件があります。
- 政府が指定する対象地域で社会的な事業を行うこと
- 補助期間内であること
- 起業地に居住すること
起業の審査を行い、上記の条件をすべて満たした場合、開業後に支援金が交付される仕組みです。
東京23区から特定の地域に移住する人に最大100万円の支援金
移住支援金は、自治体が選んだ企業に就職した人へ100万円以内の交付金が出る制度です。
ただし、単身者の場合には支援金は最大60万円となります。
この支援を受けるためには、以下のような3つの条件があります。
1.過去5年以内に東京都23区内へ住んでいた、もしくは働いていた
2.政府が指定する地域へ移住すること
3.移住予定地の自治体が指定する支援金対象の求人に就業していること
支援金を受けるためには、移住先で指定する仕事に就業、または起業することが条件となります。
こちらも詳しくは自治体に問い合わせてみましょう。
ただ、移住を決めるよりもこのような支援制度をフル活用することで、引越し代や仕事のあっせんを受けることも可能です。
移住前に、支援金を受けることも検討してみてください。
地方移住する人が参考にしたい情報サイト2選

ここまで、移住に関する情報をまとめてきました。
移住を成功させる重要ポイントとして、移住先の情報や支援制度をリサーチすることが大切だということがおわかりいただけたと思います。
このページで紹介しきれなかったお得な情報は、まだまだたくさんあります。
そこで、地方移住する人が参考にしたい代表的な情報サイトを2つ紹介していきます。
ゼロから始める田舎暮らし

ゼロから始める田舎暮らしは、豊中市の地方創生推進団体が運営している移住者のためのマッチングサイトです。
田舎で暮らすための交流会へ参加する方法や、相談会を実施している場所などを紹介しています。
また、実際に移住した人の体験談や自分に合った移住支援制度を紹介してくれるなど、移住計画を立てるためのアドバイスを聴くことも可能です。
ただし、対象エリアは大阪府や四国が中心となっているので、サイトを利用する前にどこの地域が対象なのか確認してみましょう。
JOIN

JOINは、社団法人移住・交流推進機構が運営している移住者交流支援サイトです。
上記でも触れてきましたが、地域おこし協力隊などのような就労支援情報や空き家の見つけ方などを紹介しています。
JOINは全国に対応しており、国内にある自治体からの最新情報も随時更新されています。
これから国内にある移住先を探したい人におすすめです。
まとめ
地方に移住し、田舎で暮らしを成功させるためには、移住する目的を明確にし、移住後の生活のために住処や就職先を決めておくことが大切です。
移住先の情報がわからない場合には、自治体や移住支援団体が行っている移住支援を利用しましょう。
支援には、短期間地域で生活してみるお試し移住や、農業体験なども用意されているため、まずは移住を体験してみましょう。
実際に生活してみることで、不便さや用意しなければならないものを感じることができ、今後の移住計画を立てやすくなります。
また、政府では都内から地方への移住を支援するための補助金制度を用意しています。
支度金をもらうだけでなく、就労支援を受けることも可能なので、ここまで紹介してきた情報を参考に、移住計画を検討していきましょう。